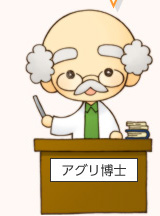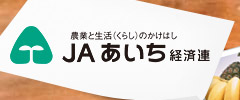最新の病害虫情報
新着情報
- 2025年12月25日【愛知県発表】予報(1月)
- 2025年12月3日【愛知県発表】予報(12月)
- 2025年12月3日【愛知県発表】スクミリンゴガイ情報第2号
- 2025年12月3日【愛知県発表】ミナミキイロアザミウマ情報第2号
- 2025年11月17日【愛知県発表】最新情報(11月)
- 2025年11月4日【愛知県発表】令和7年度病害虫発生予察特殊報第4号
- 2025年10月20日【経済連作成】 オオタバコガ情報第2報
※【愛知県発表】は愛知県が運営する「あいち病害虫情報」の情報を掲載しております。
防除のポイント(1/26更新)
![]()
| キャベツ | トマト(施設) | ナス(施設) | キュウリ(施設) |
|---|---|---|---|
| イチゴ(施設) | |||
| ※緑下線部を押すと詳細に移動します。 | ||
|---|---|---|
| ※画面右下のPAGE TOPボタンでページ上部に移動できます。 | ||
| キャベツ | ||
| コナガ | やや少ない | |
| トマト(施設) | ||
| 疫病 | 並 | |
| 灰色かび病 | 並 | |
| 葉かび病 | 並 | |
| 黄化葉巻病 | やや多い | |
| コナジラミ類 | 並 | |
| ナス(施設) | ||
| うどんこ病 | やや多い | |
| 灰色かび病 | 並 | |
| ミナミキイロアザミウマ | やや多い | |
| ハダニ類 | 並 | |
| キュウリ(施設) | ||
| べと病 | やや少ない | |
| うどんこ病 | 並 | |
| 灰色かび病 | 並 | |
| ミナミキロアザミウマ | やや多い | |
| イチゴ(施設) | ||
| 灰色かび病 | 並 | |
| うどんこ病 | 並 | |
| ハダニ類 | やや少ない | |
水稲
- スクミリンゴガイ
昨年の発生状況は概ね平年並でしたが生息地域は徐々に拡大しています。南米原産の侵入種であるこの貝の耐寒性は比較的弱く、冬期は水田や水路の浅い土中に潜って寒さに耐えています。近年は暖冬傾向であるため、生き残る貝は多い可能性があります。
【対策】
冬期のていねいな耕うんは、貝を物理的に破壊するとともに寒さに当てて殺貝する効果があります。多発した水田でまだ耕起していない場合は寒いうちに実施しましょう。貝は土中の深さ6cm程度しか潜りませんので、土壌が乾燥して固い時期にロータリーの回転数を高め浅くゆっくり細かく耕うんします。発生が多かった地域では、寒い時期に水路の泥上げを地域全体で行うと効果的であり、未発生水田への侵入防止にもなります。
また、多発した水田では均平に努めて貝が生息しやすい水深が深い地点をなくし、移植後の浅水管理による食害防止を可能にしましょう。均平化は除草剤の薬効の均一化にもつながります。
キャベツ
- コナガ
本虫は露地でも休眠せず、緩やかに生育し続けます。発生量は平年よりやや少なく推移していますが、この時期に発生があると春先の気温上昇に伴い急増する可能性があります。
【対策】
発生が見られれば、低密度のうちに薬液が葉裏にも十分かかるよう防除しましょう。主な薬剤はフィールドマストフロアブル【4E】、スピノエース顆粒水和剤・ディアナSC【5】、アファーム乳剤【6】、フローバックDF(BT剤)【11A】、モベントフロアブル【23】、ファインセーブフロアブル【34】フィールドマストフロアブル【4E】、スピノエース顆粒水和剤・ディアナSC【5】、アファーム乳剤【6】、フローバックDF(BT剤)【11A】、モベントフロアブル【23】、ファインセーブフロアブル【34】など多くありますが、本虫は同一系統薬剤の連用で薬剤の効果が低下しやすく、薬剤系統ごとのローテーション散布に心がけましょう。なお、他のアブラナ科作物もコナガは重要害虫ですが、作物の種類により適用のある薬剤は違いますので、薬剤のラベルの表示を必ず確認してください。
施設野菜
- 灰色かび病
トマト、ナス、キュウリ、イチゴなど多くの施設野菜における重要病害です。比較的低温(20℃前後)かつ多湿条件下で発生しやすくなります。昨年12月の時点では、すでに一部の施設で初発が見られました。本病の病原菌は空気伝染しやすく、いったん発生すると病斑から飛散した胞子が害虫の食害などによる傷や古い花弁が付着した部分、枯死した部分から新たに植物体内へ侵入し被害が拡大します。
【対策】
施設内の湿度をできるだけ低く保つとともに急激な温度変化による結露を防ぐよう、暖房機の温度設定や換気、送風などの環境制御に留意してください。暖冬の場合は暖房機の運転時間が短くなり、結露するなど施設内の多湿状態が続きやすくなるので注意が必要です。また、下葉の摘葉、発病果や発病葉の除去、古い花弁の摘み取りも有効です。
本病は発生するとまん延しやすく、発病初期までの予防散布に重点を置いてください。既に発生した施設では定期的な防除が必要です。また、本病は薬剤の感受性低下が起きやすいため、各作物の適用薬剤の中から異なる系統の薬剤を選択してローテーションを行います。QoI系【11】やSDHI系【7】の薬剤は治療効果があり種類も多いのですが、感受性低下が起きやすいので使用回数は必要最小限とし連用は避けてください。感受性が低下しにくく使用回数の制限がない炭酸水素カリウム剤(カリグリーン【NC】)や微生物農薬(エコショット・ボトキラー【BM02】)を、発病初期から定期的に散布する方法もあります。なお、県農業総合試験場の情報では、本病の薬剤感受性低下は地域間より作物間で異なる傾向があるため、部会内や産地で情報交換を行うと良いでしょう。
- うどんこ病
適温は25℃前後であり、他の病害に比べ施設内が比較的高温かつやや乾燥した条件で発生しやすい病害です。11月から12月にかけて平年より気温が高い時期が多かったため、ナスでは各産地で平年よりやや多く発生した施設が見られ、キュウリやイチゴでも一部の施設では発生が見られます。厳冬期の発生量はいったん減少しますが、気温が上昇すると再び増加します。灰色かび病と同様に発生するとまん延しやすいので、発生初期までの予防対策が重要です。
【対策】
ナス、キュウリ、イチゴに適用がある薬剤はベルクートフロアブル【M07】、トリフミン水和剤・スコア顆粒水和剤【3】、パレード20フロアブル・アフェットフロアブル【7】、フルピカフロアブル【9】、ショウチノスケフロアブル【9+U13】、フセキワイドフロアブル【M07+53】などがあり、各作物ごとではさらに多くの適用薬剤がありますが、本病も薬剤感受性が低下しやすいので、同一系統の薬剤に偏らないローテーション防除に努めましょう。発生初期であれば、使用回数制限がなく連用しても感受性が低下しにくいカリグリーン【NC】やジーファイン水和剤【NC+M01】を病斑に当たるよう葉裏までムラなく散布する方法があります。
トマト
- コナジラミ類・黄化葉巻病
コナジラミ類の発生量が直近数年間は以前より多い状況が続いています。本虫は吸汁害とともに排泄物によりすす病を発生させて果実の品質が低下しますが、トマトではタバココナジラミが媒介する病原ウイルス(TYLCV)による黄化葉巻病の発生が重要であり、すでに発生が多く見られる施設があります。黄化葉巻病の症状は、最初に新葉の縁が退色して葉が巻き、その後は葉がちりめん状や棒状になり裏側に巻き込み、生育は停滞し萎縮したわき芽が出ます。開花しても不稔となりやすく生産量が低下します。ウイルスを保毒したタバココナジラミは死ぬまで健全株にウイルスを感染させ続けますので、わずかな発生量でも本病は拡大します。また、タバココナジラミとオンシツコナジラミは黄化病の病原ウイルス(ToCV)も媒介します。
県内ではコナジラミ類の中でもタバココナジラミのバイオタイプQ(バイオタイプとは、外観は同じだが遺伝子型や生物学的特性が異なる系統)が優占しています。この系統は寒さに弱く本県では屋外で越冬できないとされ、この時期は施設内でのみ増殖します。
【対策】
タバココナジラミはこの時期には施設外からの侵入はなく、施設内で増殖し病原ウイルスを感染株から健全株へ媒介し続けますが、卵を経由して子孫へウイルスが伝播されることはありません。そこで、屋外から保毒虫が侵入しないこの時期に病原ウイルスの伝染環を効果的に断ち切るため、コナジラミの防除を徹底するとともに黄化葉巻病の発病株を除去しましょう。なお、黄化葉巻病耐病性品種はウイルスに感染しても病徴は出にくいのですが感染源になりますので、病原ウイルスの伝染環を断つためにコナジラミ類防除は同様に実施してください。
成虫の侵入がないこの時期に発生があれば、気温上昇時の急増を防ぐため薬剤系統間のローテーション防除を実施します。バイオタイプQの成虫は多くの薬剤で感受性が低下していますが、若齢幼虫には効果がある薬剤は多く、ベストガード水溶剤【4A】、ディアナSC【5】、アグリメック(ミニトマトは適用なし)【6】、アニキ乳剤【6】、コルト顆粒水和剤【9B】などを特定の薬剤系統に偏らないよう散布しましょう。ただし、これら薬剤も効果が低い場合は別系統の薬剤に切り替えてください。サフオイル乳剤【未】などの気門封鎖剤は薬剤抵抗性が生じる可能性は低く、少発生時に虫体に十分かかるよう7日間隔で2~3回程度散布します。なお、トマトとミニトマト(農薬登録上の分類では果径3cm以下のトマト)では適用薬剤や使用方法は違いますので、必ずラベルの表示事項を確認して使用してください。また、訪花昆虫やタバコカスミカメなどの天敵を導入している場合はこれらに影響日数が長い薬剤もあるので、訪花昆虫や天敵の購入元や農薬の販売店、指導機関等に確認して薬剤を選定してください。 - 葉かび病
多湿条件で発生しやすく、灰色かび病と同様に今後の発生に注意してください。なお、葉かび病抵抗性品種に葉かび病に似た病徴が(主に葉裏)発生したら、すすかび病が疑われます。すすかび病は葉かび病よりもやや高温で発生しやすいことや裏面のかびが盛り上がりがないことから大まかに判別できます。
【対策】
灰色かび病対策と同様に急激な温度の変化をなくし結露させない温度管理に心がけるとともに、施設内の送風や換気に努めて湿度を低下させる環境制御を行いましょう。下葉の摘葉やマルチも有効です。すすかび病を含め適用がある主な薬剤は、予防効果が高いペンコゼブフロアブル【M03】、治療効果もあるラリー乳剤・トリフミン乳剤【3】などです。灰色かび病も含め適用がある主な薬剤は、予防剤としてダコニール1000【M05】、治療効果もある剤としてニマイバー水和剤【1+10】、アフェットフロアブル・パレード20フロアブル【7】、ファンタジスタ顆粒水和剤【11】などですが、同一系統の薬剤に偏らないローテーション防除に努めましょう。
ナス
- ミナミキロアザミウマ
発生量はやや多い予想であり、12月にも本虫の食害により果実にキズが発生していた施設も見られたため注意は必要です。初期被害は葉裏にシルバリングと呼ばれる銀白色の吸汁痕ができ、その後、葉表の葉脈沿いにかすり状の被害が見られます。果実では低密度でも縦線状の褐色の傷や裂果ができ商品価値を損ねます。
【対策】
白色で舞いやすいコナジラミ類成虫に比べると目立たず初期発生に気付きにくいので、青色粘着板で発生を確認したり果実などの被害を確認したら早めに防除します。ベストガード水和剤【4A】、ディアナSC【5】、アグリメック【6】、モベントフロアブル【23】、グレーシア乳剤【30】、ファインセーブフロアブル【34】などタバココナジラミにも適用がある薬剤は多くありますので、同時防除も考慮して使用回数を最小限にとどめましょう。また、コナジラミ類と同様に薬剤感受性が低下しやすいので、同一系統の薬剤を連用しないよう注意してください。訪花昆虫を導入している場合は、薬剤の影響日数にも注意が必要です。なお、天敵農薬であるスワルスキーカブリダニ剤(スワルバンカーロングなど)をコナジラミ類防除と兼ね定植後から導入する方法もありますので、次作ではご検討ください。
キュウリ
- ミナミキロアザミウマ
発生量はやや多い予想であり、この時期に発生があると春先に急増する可能性があります。発生密度が高いと葉だけでなく果実の食害も発生しますが、黄化えそ病の病原ウイルス(MYSV)を媒介することから少発生でも防除は徹底しておきましょう。
【対策】
本虫は肉眼では見つけにくいため青色粘着板や葉の被害などで発生の早期把握を心がけ、発生があれば早めに防除しましょう。適用のある薬剤はアファーム乳剤・アグリメック【6】、コテツフロアブル【13*】、モベントフロアブル【23】、ベネビアOD【28】、グレーシア乳剤【30】、プレオフロアブル【UN*】など多いのですが、薬剤感受性が低下しやすいので必ず同一系統の薬剤に偏らないローテーション防除を実施します。また、本虫は花や新芽などの隙間を好み生息していますので、ていねいに散布してください。
天敵農薬のスワルスキーカブリダニ剤(スワルバンカーロングなど)は、本虫の発生を長期間抑制して化学農薬の使用回数を削減するとともに、化学農薬の連用による薬剤感受性の低下を防ぐことも期待できます。春先から導入を予定している施設では、有機りん系【1B】やピレスロイド系【3A】、一部のネオニコチノイド系【4A】など天敵に長期間影響のある薬剤がありますので、天敵購入先等に確認して天敵放飼前は天敵への影響日数が短い薬剤を使用し、害虫の密度をごく低くしてから導入してください。
- べと病
発生量はやや少ない予想ですが本病は気温20〜24℃で多湿時に多発しますので、春の気温上昇とともに再び多発しやすい環境になります。本病は葉脈に区切られた角型の病斑ができ、葉裏には薄いビロード状のカビが見られます。
【対策】
暖房機のダクト送風運転、天窓等の開閉により過湿にならず結露させない環境管理を行いましょう。また、樹勢が低下すると発病しやすいので、適度な追肥や摘果で樹勢を維持しましょう。適用のある薬剤はジマンダイセン水和剤【M03】、ダコニール1000【M05】のような予防効果の高い保護殺菌剤や、アリエッティC水和剤【P07+M04】、フェスティバルC水和剤【40+M01】、プロポーズ顆粒水和剤【40+M05】、ベジセイバー【7+M05】などの予防と治療を兼ねた薬剤がありますが、多発すると病勢が止まりにくいため、まずは予防に重点を置いた定期的なローテーション防除が大切です。病勢が進展するなら発病葉は除去して施設外で処分し、4~5日間隔の連続散布で防除しましょう。
イチゴ
- ハダニ類
発生は全体にはやや少ない予想ですが、昨年秋は比較的気温が高く推移したため多発した施設も見られました。冬期にも発生が続いていると、春の気温上昇時に多発する可能性があります。
【対策】
下葉かきを徹底するとともに、スポット的に発生し始める初期段階を早期発見し、マイトコーネフロアブル【20D】、スターマイトフロアブル【25A】、ダニコングフロアブル【25B】などで被害が広がる前に防除します。薬剤の感受性が低下しやすいため、同一系統の薬剤は1作で1回までの使用としましょう。ピタイチやサフオイル乳剤、エコピタ液剤などの気門封鎖剤【未】は薬剤感受性が低下しにくいため、5~7日間隔で虫体に直接かかるよう葉裏にも十分に散布しましょう。なお、気門封鎖剤の中には環境条件により薬害が発生しやすい場合がありますので、ラベルの注意事項を確認するとともに数株で試行すると良いでしょう。
最近は化学農薬だけに頼らず、天敵農薬であるミヤコカブリダニ剤(ミヤコバンカー等)やチリカブリダニ剤(チリガブリ等)を利用する施設が増加しています。次作ではご検討ください。なお、天敵は放飼前に天敵への影響日数を考慮した薬剤による防除でハダニ類の密度をできるだけ低くしておくことが望ましいので、天敵購入先等にご相談ください。
☆薬剤名に続く【 】内の数字や記号はIRACコード(殺虫剤)、FRACコード(殺菌剤)で薬剤の系統を表し、同じ数字や記号は同じ系統の薬剤です。農薬は使用する前にラベル等で登録内容、注意事項等を確認してからご使用ください。