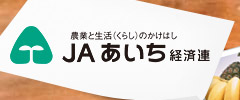最新の病害虫情報
新着情報
- 2025年6月12日【愛知県発表】病害虫発生予察特殊報第2号(ナガエツルノゲイトウ)
- 2025年6月2日【愛知県発表】予報(6月)
- 2025年6月2日【愛知県発表】斑点米カメムシ情報第1号(イネカメムシ対策)
- 2025年5月22日【愛知県発表】病害虫発生予察注意報第2号(果樹カメムシ類)
- 2025年5月16日【愛知県発表】最新情報(5月)
- 2025年5月16日【愛知県発表】ナシマルカイガラムシ情報第1号
- 2025年5月16日【愛知県発表】フジコナカイガラムシ情報第1号
- 2025年4月17日【愛知県発表】病害虫発生予察1号(コムギ縞萎縮病)
- 2025年4月8日【経済連作成】 コムギ赤かび病情報
- 2025年4月8日【経済連作成】 果樹カメムシ類情報
- 2025年4月7日【愛知県発表】予報(4月)
- 2025年4月7日【愛知県発表】ムギ類赤かび病情報第1号(コムギ、六条大麦)
- 2025年4月7日【愛知県発表】スクミリンゴガイ情報第1号
- 2025年4月7日【愛知県発表】果樹カメムシ類情報第1号
- 2025年4月7日【愛知県発表】灰色かび病情報第1号 (キュウリ、イチゴ、トマト、ナス)
※【愛知県発表】は愛知県が運営する「あいち病害虫情報」の情報を掲載しております。
今月の防除のポイント(6/16 更新)
![]()
| イネ | ウンシュウミカン | ナシ | モモ |
|---|---|---|---|
| ブドウ | 果樹共通 | キク(露地) | |
| ※緑下線部を押すと詳細に移動します。 | ||
|---|---|---|
| ※画面右下のPAGE TOPボタンでページ上部に移動できます。 | ||
| イネ | ||
| いもち病 | 並 | |
| 紋枯病 | 並 | |
| 縞葉枯病 | 並 | |
| ニカメイガ | やや多い | |
| ヒメトビウンカ | 並 | |
| 斑点米カメムシ類 | 多い | |
| スクミリンゴガイ | やや多い | |
| ウンシュウミカン | ||
| そうか病 | やや多い | |
| 黒点病 | やや少ない | |
| ミカンハダニ | 少ない | |
| アブラムシ類 | やや少ない | |
| チャノキイロアザミウマ | 並 | |
| ナシ | ||
| 黒星病 | 並 | |
| アブラムシ類 | やや多い | |
| モモ | ||
| せん孔細菌病 | やや少ない | |
| 黒星病 | 並 | |
| 灰星病 | 並 | |
| ナシヒメシンクイ | やや多い | |
| モモハモグリガ | 並 | |
| ブドウ | ||
| べと病 | 並 | |
| 黒とう病 | やや多い | |
| チャノキイロアザミウマ | 並 | |
| カキ | ||
| 炭疽病 | 並 | |
| 角斑落葉病 | やや少ない | |
| 円星落葉病 | やや多い | |
| うどんこ病 | やや少ない | |
| 果樹共通 | ||
| 果樹カメムシ類 | やや多い | |
| キク(露地) | 白さび病 | 並 |
イネ
- いもち病(葉いもち)
葉いもちは湿潤条件が10時間以上続くと感染しやすく、降雨が長時間続くと発生が増加します。感染すると1週間後頃から葉に紡錘型の病斑が生じ、梅雨期のように湿潤条件が続くと急速に感染が進むといわゆる「ずりこみいもち」となり、生育が止まり稲全体が燃えたように萎縮し枯れ上がる被害が出ることもあります。
昨年も、コシヒカリなど本病に弱い品種では発生が見られたほ場がありました。発生ほ場では病原菌が残り、今年も発生する可能性があります。あいちのかおりSBLなど穂いもちに強い抵抗性がある品種でも、不適地に栽培したり天候が不順だと葉いもちが発生する場合があります。本病に適用がある箱施薬剤を散布してなかったり降雨が続くなど本病が発生しやすい気象条件が続けば注意してください。なお、品種更新されたミネアサヒSBLは、葉いもち、穂いもちともに強い抵抗性があります。
【対策】
葉に病斑を確認したら、オリブライト250G【11】やブラシンフロアブル【U14+16.1】などで防除しましょう。病斑が少なくても湿潤条件が続き、病斑の中央部が灰白色で周縁が紫黒色の病斑が見られたら急性型であり、急速に被害が広がりますので早急に防除しましょう。補植用の苗は本病が発生しやすく伝染源になりますので、補植が終われば速やかに除去しましょう。
- 紋枯病
発生量は平年並の予想ですが、前年に本病が多発した水田では稲わらや土壌に病原菌の菌核が残り、今年度も発生が多くなる可能性があります。初期は水際に近い葉鞘に水浸状のやや大型の病斑が見られ周辺に広がります。その後、梅雨期が比較的高温になると病斑は上位葉へ進展し、捻実が悪くなり減収につながります。また、葉鞘の発病は倒伏を助長します。なお、近年の夏季の高温で病斑が停滞する場合がありますが、普通期栽培では8月下旬以降の気温低下とともに上位葉に進展し、多発する事例があります。
【対策】
発病株率が概ね10〜20%以上になれば、幼穂形成期から穂ばらみ期にモンカット粒剤【7】やリンバー粒剤【7】などで病斑の上位進展を防ぎ、止まらずに多発しそうなら、出穂期にかけてバリダシン液剤5【U18】などの速効性の薬剤で防除しましょう。なお、例年発生が多いほ場は、次年度は育苗箱施薬や種もみ塗抹等で本病にも適用がある薬剤を利用しましょう。
- 縞葉枯病
本病に感染すると新葉が黄白色になり、こより状に垂れ下がって「ゆうれい症状」となって枯死します。生育後期では、葉が黄白色の縞模様となり穂が出すくむ場合もあります。
本病はウイルス病であり、病原ウイルスを保毒したヒメトビウンカ(以下、ヒメトビとします。)が稲を吸汁すると感染します。このウイルスはヒメトビの世代間で経卵伝染するため、一度保毒すると次世代に永続伝染します。ヒメトビはイネ科雑草で越冬し、春にはムギで増殖してから水田に飛来するため、小麦の栽培地域は本病の発生が多くなる場合があります。
本県の奨励品種の多くはいもち病と同様に抵抗性がありますが、例年、本病の発生が見られる地域でコシヒカリなどの感受性品種を栽培している場合は注意が必要です。
【対策】
ウイルス病のため発病後の治療は困難です。本病の発生地域で感受性品種を栽培しているが、ヒメトビを対象とした育苗箱施薬や種もみ塗抹等を実施してなければ、トレボン乳剤【3A】やスタークル液剤10【4A】などを本田散布してヒメトビを防除し、本病の感染拡大を防ぎます。
- ニカメイガ
かつてはイネの重要な害虫でしたが、近年の発生量は減少していました。しかし、最近では再び発生量が増加傾向であり、麦あとの水稲でほ場全面が加害された事例もありました。昨年も、第1世代幼虫による心枯れの被害や第2世代幼虫による白穂が散見された地域がありました。今年も県内各地で成虫が平年より早くかつ多く誘殺されています。
【対策】
平年では6月中下旬に越冬世代成虫発生の最盛期となり、その7〜15日後頃が防除適期とされています。成虫の被害が多いほ場や箱施薬等の予防がされていない場合は、県発生予察情報(愛知病害虫情報)の誘殺数や流れ葉などの初期被害を参考にして、パダンSG水溶剤【14】やディアナSC【5】などを散布します。
- 斑点米カメムシ類
最近多発しているイネカメムシは、県内各地で出穂直後から多発し不稔籾や斑点米を生じさせ減収や等級低下の原因となっています。このカメムシはイネの穂が大好物であり、越冬した成虫は畦畔雑草を経由せずに出穂前から水田に直接飛来します。特にあきたこまちやコシヒカリなど地域で最も出穂が早いほ場に集中して飛来します。飛来した越冬成虫は穂を加害するとともに出穂期頃のイネに産卵し、次世代幼虫も穂を加害します。越冬成虫や次世代の成虫は、近隣の次に出穂するほ場に移動して産卵や食害を行います。
【対策】
イネカメムシと他の斑点米カメムシ類では防除適期が違います。イネカメムシでは、まず不稔籾対策のため出穂期(穂の先端が顔を出した茎が全体の半数の時期。)を逃さないように、スタークル(液剤10、顆粒水溶剤)【4A】やエクシードフロアブル【4C】、キラップフロアブル【2B】を散布します。多発時は散布後7〜10日後に再度散布して斑点米の発生も防ぎましょう。薬剤防除を2回実施する場合、1回目と2回目の薬剤はなるべく系統の違う薬剤を使用して、感受性の低下を防ぎましょう。なお、キラップ剤はイネカメムシの感受性が低下した地域がありますので、効果が低い情報があれば他の剤に切り替えてください。
イネカメムシとともにミナミアオカメムシなど他の斑点米カメムシ類の発生があり斑点米が問題となる地域では、2回目の薬剤防除は出穂7〜14日後頃を目安とします。耕種的な対策として出穂2週間前までを目安として畦畔など水田周辺の草刈りと本田内のヒエ類の除去を行い、カメムシ類の棲み家をなくします。ただし、出穂間際の除草はカメムシ類を本田内に追い込みますので、やむを得ず除草する場合は本田防除を併せて行います。なお、イネカメムシは畦畔除草の効果があまりありません。
- スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
普通期栽培で昨年被害を受けた水田では、貝が苗を摂食しなくなる5葉期頃(移植3週間後頃)までは食害に注意が必要です。
【対策】
例年発生が多い水田では移植後3週間程度は水深4cm以下の浅水管理を行い、貝の食害を防ぎましょう。貝の発生が多ければ、スクミノンやジャンボたにしくん、スクミンベイト3などの薬剤を散布します。水深の深い場所や取水口周辺など発生が多い地点に、スポット的に散布する方法もあります。なお、水田では除草剤を含め薬剤散布したら、1週間以上は落水しないでください。
スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の被害防止対策について(農林水産省HP)
ウンシュウミカン
- そうか病、黒点病
そうか病は発病葉がやや多い園地があります。この時期は雨を介して若い葉や幼果に感染し、さらに他の葉や果実に二次感染していきますので、梅雨明けまでは感染拡大に注意が必要です。黒点病も枯れ枝や落ちているせん定枝上の胞子が伝染源となり、雨滴により胞子が果実や葉へ伝搬して感染が広がります。発生量はやや少ない予想ですが、そうか病と同様に梅雨期は果実へ感染しやすい時期です。
【対策】
そうか病と黒点病との同時防除として、ファンタジスタ顆粒水和剤【11】やフルーツセイバー【7】、ナティーボフロアブル【3+11】などを散布しましょう。なお、ベンレート水和剤【1】とトップジンM水和剤【1】は感受性が低下した事例があり、使用は控えたほうが良いでしょう。
- ミカンハダニ
5月の発生量は全体には少ない状況ですが、各産地で少発生の園地も見られます。気温の上昇で急増する場合があります。
【対策】
園地内の例年発生が早い地点で発生状況を観察し、早期発見により多発前の初期防除を行います。適用薬剤はコロマイト水和剤【6】やカネマイトフロアブル【20B】、マイトコーネフロアブル【20D】、ダニゲッターフロアブル【23】など多いのですが、薬剤抵抗性が発達しやすいため各薬剤の使用回数は年1回に止め、系統の違う薬剤をローテーション散布します。アタックオイルなどのマシン油剤はハダニの抵抗性が発達しにくく使用回数制限もなく使いやすいのですが、殺菌剤のデランフロアブルとの近接散布は薬害が発生する場合があり、30日以上間隔を空けてください。なお、アザミウマ類等の害虫防除に有機リン系【1B】やピレスロイド系【3A】の薬剤を連用すると土着天敵が減少しハダニが増加することもあるので、ハダニが多発しやすい園ではなるべく使用を控えたほうが良いでしょう。
- チャノキイロアザミウマ
5月の発生量は平年並です。本虫は多くの植物に寄生し、防風垣のイヌマキやサンゴジュでも発生して園内に飛来します。この時期にミカンに飛来すると果皮とがくの隙間に潜んで加害するため、果梗部にリング状の傷ができます。ブドウでは葉や穂軸に淡褐色のかすり状の斑点や褐変、果実では灰白色の輪状や雲状のさび果となり肥大が妨げられ、商品価値が低下します。
【対策】
県の予測(6月2日時点)では、防除適期である成虫の発生ピークは6月11日(名古屋)〜6月18日(南知多)頃、次のピークは7月2日(名古屋)〜7月10日(南知多)頃と予想されています。スタークル顆粒水溶剤【4A】、ダントツ水溶剤【4A】、コルト顆粒水和剤【9B】、コテツフロアブル【13*】等で防除します。ブドウでは袋かけを早めに行い、止め金を穂軸にしっかりつけて隙間をなくします。ただし、多発時は穂軸の加害や袋内への侵入もありますので、袋かけ後も防除が必要です。
ナシ
- 黒星病
発生量は平年並と予想されていますが、5月下旬には各産地で発病葉が見られ、発病果も一部の園地で確認されています。本病の胞子は降雨で水分を得て飛散するため、果実への二次感染を防止するために梅雨期も引き続き定期的な防除が必要です。
【対策】
発病葉や発病果は除去するとともに、昨年多発した園やすでに発生した園では、オーソサイド水和剤80【M04】やベルクート水和剤【M07】などの予防剤とともに、スコア顆粒水和剤などのDMI系【3】、カナメフロアブル・パレード15フロアブルなどのSDHI系【7】、ナリアWDG【7+11】など治療効果のある薬剤で、降雨の合間にかけ残しがないよう定期的な防除を継続しましょう。治療効果のある薬剤は耐性菌が発生しやすいので同一系統の連用は避けましょう。 - アブラムシ類
5月下旬の新梢での発生量が園地が平年よりやや多く見られ、多発した園地もあります。
【対策】
適用のある薬剤は多いのですが他の害虫との同時防除も考慮し、シンクイムシ類やカイガラムシ類との同時防除ができるオリオン水和剤40【1A】やモスピラン顆粒水溶剤【4A】、カイガラムシ類との同時防除ができるトランスフォームフロアブル【4C】やコルト顆粒水和剤【9B】などを選択するなど、薬剤の散布回数が過剰にならないよう効率的に選択してください。
モモ
- せん孔細菌病
本病は梅雨期の降雨で風を伴うと、枝の病斑(亀裂やカサブタ状)や葉の病斑(褐変し穴があく)から病原細菌が飛散し、気孔や傷口から侵入して健全な葉や果実に感染します。5月の発生量はやや少ない状況ですが、今後の降雨が多いと感染が拡大する可能性があります。
【対策】
本病の病原は細菌のため治療剤はごく少なく、感染予防に努めましょう。作業時などで見つけた発病枝や発病葉は除去し、園外に持ち出して伝染源を減らしましょう。また、例年発生する園では果実への感染防止のため早めに袋かけを行いましょう。薬剤は10〜14日間隔でバリダシン液剤5【U18】、マイコシールド【41】、スターナ水和剤【31】などを雨間に散布します。なお、収穫時期が近いため、薬剤散布時は薬剤のラベルに記載のある収穫前日数を必ず確認してください。
- ナシヒメシンクイ
越冬世代の成虫がモモやウメの新梢などに産卵し、その幼虫が新梢先端に移動して食入し芯折れを起こします。県の情報によれば、フェロモントラップへの成虫の誘殺数の最初のピークは4月上中旬頃で平年よりやや遅かったのですが、誘殺数は平年より多い地域があり、平年より多発する可能性があります。また、今後はナシに飛来し果実を加害しますので、ナシ園でも今後の多発に注意してください。
【対策】
芯折れした枝は、食害されていない部分を含め切除しましょう。今後は世代が進むにつれ成虫が途切れなく発生しますので、芯折れの発生が多かったり毎年被害がある園地では、定期的な薬剤散布を行い果実への食入を防止しましょう。モモの主な適用薬剤として、オリオン水和剤40【1A】やモスピラン顆粒水溶剤・ダントツ水溶剤【4A】、テッパン液剤【28】などがあります。
ブドウ
- べと病
発生量は平年並ですが、5月下旬には発病葉が目立つ園地もあります。べと病菌は発病適温が22〜25℃であり雨水により移動・感染するため、梅雨期は柔らかい葉や新梢に短期間で感染が広がりやすく、予防対策が重要です。
【対策】
発病葉や発病果は感染源となるため、園外に持ち出し処分します。また、袋かけまでは降雨前や雨間に10日程度の間隔で予防散布に努めましょう。適用のある薬剤は収穫前日数が比較的長い品目が多く、収穫前日数が比較的短い薬剤はランマンフロアブル【21】(収穫14日前まで)やホライズンドライフロアブル【11+27】(収穫21日前まで)など少ないので、系統間のローテーションも考慮し計画的に薬剤を選定してください。また、薬剤によっては幼果の大きさにより果粉溶脱や薬害を生じる事例がありますので、使用する際はラベルの収穫前日数とともに注意事項を必ず確認してください。袋かけ後は、使用時期の制限がない無機銅剤で防除しましょう。なお、QoI剤【11】のアミスター10フロアブルとストロビードライフロアブルは耐性菌が確認されていますので、本病には使用は控えたほうが良いでしょう。
- 黒とう病
すでに新梢に発病が確認された園地が比較的多く、発生量は平年よりやや多い予想です。本病はべと病と同様に雨滴で発病新梢や発病葉の胞子が飛散して二次感染しますので、降雨が続くと発病が急増します。シャインマスカット等の欧州系品種は、本病に弱い傾向があります。
【対策】
発病部位は見つけ次第除去し、園外へ持ち出し処分しましょう。梅雨明けや袋かけまで晩腐病との防除を兼ねた定期的な散布が必要であり、降雨前の予防散布が効果的です。オンリーワンフロアブル【3】、カナメフロアブル【7】、スクレアフロアブル【11】、ホライズンドライフロアブル【11+27】などで予防散布を行います。べと病にも適用がある薬剤は少ないので、同時防除を行う場合は薬剤のラベルを確認し、計画的に薬剤を選択してください。また、収穫前日数及び果粉溶脱等の薬害が発生しないよう、ラベルの注意事項を必ず確認してください。
- チャノキイロアザミウマ
5月の発生量は平年並です。本虫は多くの植物に寄生し、防風垣のイヌマキやサンゴジュでも発生して園内に飛来します。この時期にミカンに飛来すると果皮とがくの隙間に潜んで加害するため、果梗部にリング状の傷ができます。ブドウでは葉や穂軸に淡褐色のかすり状の斑点や褐変、果実では灰白色の輪状や雲状のさび果となり肥大が妨げられ、商品価値が低下します。
【対策】
県の予測(6月2日時点)では、防除適期である成虫の発生ピークは6月11日(名古屋)〜6月18日(南知多)頃、次のピークは7月2日(名古屋)〜7月10日(南知多)頃と予想されています。スタークル顆粒水溶剤【4A】、ダントツ水溶剤【4A】、コルト顆粒水和剤【9B】、コテツフロアブル【13*】等で防除します。ブドウでは袋かけを早めに行い、止め金を穂軸にしっかりつけて隙間をなくします。ただし、多発時は穂軸の加害や袋内への侵入もありますので、袋かけ後も防除が必要です。
カキ
- 炭疽病
発生量は平年並の予想ですが、「富有」「早秋」では本病が発生しやすい傾向があります。病原菌は主に雨水により胞子が飛散して感染が広がりますので、降雨が続くと発病しやすくなります。最初は新梢に円形から楕円形の病斑が形成され、新梢に発病が多いと果実の発病も多くなります。
【対策】
梅雨期が主要な感染時期である落葉病との同時防除が効果的です。月2回程度でペンコゼブ(ジマンダイセン)水和剤【M03】やオーソサイド水和剤80【M04】などで予防散布を行いましょう。
- うどんこ病
発生量はやや少ない予想ですが、既に発病葉が見られる園地もあります。本病は若い葉の葉裏に小黒点の病斑が発生し、病斑上の分生胞子が風で飛散し二次感染を起こします。発病葉は早期に落葉します。
【対策】
発生が見られ始めると急激にまん延しやすいので、初発時を逃さずに防除を行います。この時期に発生がある園地では、オンリーワンフロアブル【3】やスコア顆粒水和剤【3】、ナリアWDG【7+11】など、落葉病や炭疽病にも適用のある薬剤で同時防除する方法があります。なお、同一系統の薬剤は連用しないよう注意しましょう。
- 落葉病類
円星落葉病や角斑落葉病がありますが、いずれも主要な感染時期は梅雨期であり、病斑が目立ち始める8月以降の散布では防除効果が見込めません。
【対策】
例年発生する園地では、梅雨期に上記の炭疽病やうどんこ病で記載した薬剤による予防散布を行いましょう。なお薬剤のラベル上の病害虫名は、円星落葉病や角斑落葉病ともに「落葉病」です。
果樹全般
- 果樹カメムシ類
果樹を加害するカメムシ類(チャバネアオカメムシ及びツヤアオカメムシなど)の発生は多く、一部の果樹園では既に加害が確認されています。このため、県では5月22日に注意報を発表し、飛来の早期発見と発見後の速やかな防除を呼び掛けています。最近では、主要種である前翅が茶色のチャバネアオカメムシだけでなく、体表面がすべて光沢の強い緑色のツヤアオカメムシの発生も増加しています。両種の生態や防除対策はほぼ同様です。
【対策】
周辺の園を含め飛来を確認したら、ネオニコチノイド系薬剤【4A】など速効かつ比較的残効のある薬剤で防除します。果樹の品目で適用のある薬剤は違うため、収穫前日数などを含め薬剤のラベルを必ず確認してください。なお、薬剤による飛来前の予防は困難です。他の害虫防除を含め同一系統薬剤の連用や在来天敵、ハチなどへの影響を防ぐため、発生状況に応じた使用に留めましょう。
露地ギク
- 白さび病
発生量は平年並の予想ですが、山間部では5月には発病が確認されたほ場があり注意が必要です。梅雨期に感染が拡大する場合があります。
【対策】
まん延後の防除は困難になりますので、予防散布が重要です。発病初期なら、病斑のある葉を摘み取ってから散布すると良いでしょう。潜伏期間は1週間程度ですので、散布1週間後に観察して病斑の発生している葉があれば摘み取りましょう。本病に適用のある薬剤はラリー乳剤【3】やカナメフロアブル【7】など多数ありますが、系統ごとにローテーション防除を行い、薬剤の感受性を低下させないよう注意してください。
☆薬剤名に続く【 】内の数字や記号はIRACコード(殺虫剤)、FRACコード(殺菌剤)で薬剤の系統を表し、同じ数字や記号は同じ系統の薬剤です。農薬は使用する前にラベル等で登録内容、注意事項等を確認してからご使用ください。
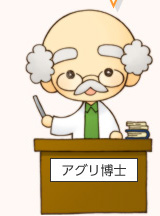
- 2025/6/16 今月の防除ポイント概要を更新しました。
- 2025/5/22 今月の防除ポイント概要を更新しました。"
- 2025/5/7 今月の防除ポイント概要を更新しました。"
- 2025/4/10 今月の防除ポイント概要を更新しました。"