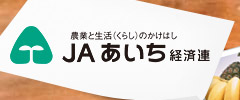最新の病害虫情報
新着情報
- 2025年10月1日【愛知県発表】予報(10月)
- 2025年10月1日【愛知県発表】水稲の秋期管理情報第1号
- 2025年10月1日【愛知県発表】吸実性カメムシ類情報第2号
- 2025年10月1日【愛知県発表】ハスモンヨトウ情報第2号
- 2025年10月1日【愛知県発表】キャベツ黒腐病情報第1号
- 2025年10月1日【愛知県発表】コナジラミ類情報第2号
- 2025年9月17日【愛知県発表】最新情報(9月)
- 2025年9月17日【愛知県発表】オオタバコガ情報第4号
- 2025年8月15日【経済連作成】 シロイチモジヨトウ情報第1報
- 2025年8月15日【経済連作成】 ハスモンヨトウ情報第1報
※【愛知県発表】は愛知県が運営する「あいち病害虫情報」の情報を掲載しております。
今月の防除のポイント(10/23更新)
![]()
| ダイズ | ナシ | カキ | ウンシュウミカン |
|---|---|---|---|
| ハクサイ | キャベツ | トマト(施設) | イチゴ(施設) |
| 野菜共通 | キク(露地) | ||
| ※緑下線部を押すと詳細に移動します。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ※画面右下のPAGE TOPボタンでページ上部に移動できます。 | ||||
| ダイズ | ||||
| ハスモンヨトウ | やや多い | |||
| シロイチモジヨトウ | やや多い | |||
| 吸実性カメムシ類 | やや多い | |||
| ナシ | ||||
| 黒星病 | 少ない | |||
| カキ | ||||
| 炭疽病 | やや少ない | |||
| カメムシ類 | 並 | |||
| ウンシュウミカン | ||||
| カメムシ類 | 並 | |||
| ハクサイ | ||||
| べと病 | 並 | |||
| コナガ | やや多い | |||
| ハイマダラノメイガ | やや多い | |||
| アブラムシ類 | 並 | |||
| キャベツ | ||||
| 黒腐病 | やや多い | |||
| オオタバコガ | やや多い | |||
| コナガ | やや多い | |||
| ハイマダラノメイガ | やや多い | |||
| トマト(施設) | ||||
| 葉かび病 | 並 | |||
| すすかび病 | やや少ない | |||
| 黄化葉巻病 | やや多い | |||
| コナジラミ類 | やや多い | |||
| イチゴ(施設) | ||||
| うどんこ病 | 並 | |||
| 炭疽病 | やや多い | |||
| ハダニ類 | やや多い | |||
| 野菜共通 | ||||
| ハスモンヨトウ | やや多い | |||
| シロイチモジヨトウ | やや多い | |||
| 野菜共通 | ||||
| ハスモンヨトウ | やや多い | |||
| オオタバコガ | 多い | |||
ダイズ
- ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ
両種は形態や生態が類似しますが、老齢幼虫はハスモンヨトウの方が大きく、幼虫の背面の頭の後ろに1対の黒斑があるので判別できます。いずれも毛に覆われた卵塊を葉裏に産みますがハスモンヨトウは黄褐色、シロイチモジヨトウは灰白色です。どちらも若齢幼虫は集団で食害しダイズでは白変葉を生じます。両種が混在する場合もあります。
両種とも多発した昨年よりは発生が少ないのですが、高温傾向のため成熟期近くまで食害を起こす可能性があります。特にハスモンヨトウは老齢幼虫になると暴食するため、早期防除が大切です。多発した場合は防除を実施しても次々と成虫が飛来し産卵するため、継続した防除が必要になっています。
【対策】
防除しても新たな白変葉が見られるなど発生が続く場合は、各薬剤の収穫前日数など使用基準を遵守して、ハスモンヨトウにはトルネードエースDF【22A】、ブロフレアSC【30】、プレオフロアブル【UN】などで防除しましょう。シロイチモジヨトウにはダイズの適用薬剤はブロフレアSC【30】、プレオフロアブル、微生物農薬であるBT剤【11A】しかないため、ハスモンヨトウの発生があればハスモンヨトウの防除を主とします。いずれも、老熟幼虫になると効果が低下します。また、両種とも一部の薬剤に対し抵抗性が発現した事例があり、若齢幼虫が生き残るなら他系統の薬剤に切り替えてください。
- 吸実性カメムシ類
ミナミアオカメムシの誘殺数が多い地域があります。特に近隣の水稲からダイズ畑に多数飛来し子実を吸汁する可能性があります。
【対策】
カメムシ類の発生が多ければ、スタークル顆粒水溶剤やダントツ水溶剤【4A】、キラップフロアブル【2B】等で早急に防除しましょう。ヨトウ類と同様に収穫前日数に注意してください。
ナシ
- 黒星病
今作の発生量は高温のためか少ない状況でしたが、この時期は葉裏に黒いしみ状の病斑(秋型病斑)ができ、落葉すると翌春にこの落葉から胞子が発生したり発病葉からりん片へ伝染して翌年の伝染源になります。
【対策】
発生園では越冬伝染源をなくすため、発病葉や落葉を園外へ持ち出し処分しましょう。また、りん片への感染防止のため、ICボルドー48Q、オキシンドー水和剤80などの銅剤【M01】を、落葉する11月上中旬頃までに2回程度散布しましょう。
カキ
- 炭疽病
本病は枝や果実に暗褐色の円形の斑点が現れ、果実では早く着色して落下します。9月の発生量はやや少なかったのですが降雨時に胞子が飛散して感染が拡大するため、本病に比較的弱い「早秋」や「富有」では降雨が続けば果実での発生に注意してください。
【対策】
発生園では次作への伝染源を減らすために発病枝や発病果を除去するとともに、収穫まで日数があればスコア顆粒水和剤【3】やナリアWDG【7+11】(いずれも収穫前日まで)などを散布します。すでに収穫時期に入っている品種も多いのでラベルに記載された収穫前日数を厳守するとともに、隣接園への飛散防止に努めてください。
- 果樹カメムシ類
この時期は夏にスギやヒノキ林で育った成虫が林から離脱し、果樹園に飛来すると果実を加害します。昨年は県内外で多発し大きな被害がありましたが、今年は果樹園への飛来は平年並です。しかし、今後の気象条件の急激な変化(台風通過や雨後の気温上昇等)や越冬地への移動途中に集団で飛来する可能性はあります。しばらくは発生に注意してください。
【対策】
飛来前の薬剤の予防散布は効果が低いため、飛来を確認したらスタークル顆粒水溶剤やダントツ水溶剤【4A】、アグロスリン水和剤【3A】など速効性のある薬剤で防除しましょう。散布時は薬剤のラベルに記載された収穫前日数を厳守するとともに、隣接園地や養蜂、養魚池など周辺環境に飛散しないよう注意してください。
ハクサイ
- べと病
病原菌が雨水によって飛散し作物に付着すると、葉裏の気孔や細胞の境目などから侵入し、葉脈に囲まれた角形の病斑を生じます。ハクサイでは品種間で発病差があり、黄心系の多くの品種では「茎べと」と呼ばれる中肋内部が黒変する症状を示すことがあります。10〜11月の結球開始期以後に降雨があると発生しやすくなります。
【対策】
ほ場の排水対策に努めましょう。また、降雨前後にランマンフロアブル【21】などを葉裏や株元に十分かかるように散布しましょう。発病株があれば、リドミルゴールドMZ【4+M03】など治療効果が高い薬剤を散布して周辺の健全株への感染拡大を防ぎます。 - ハイマダラノメイガ
各地で発生が見られます。今後の気温も平年より高い予想から、定植が遅い作型では例年以上に発生に注意してください。本虫は、作物の生育初期は中心葉の生長点部に潜って加害するため発見が遅れやすく、生育が停止したり正常に結球しない場合があります。生育中期以降は葉柄内への食入被害が多く、糞の排出や葉柄が垂れ下がります。
【対策】
定植後は早期発見に努め、ディアナSC【5】やプレバソンフロアブル【28】などを散布しましょう。なお、次項のヨトウ類との同時防除が可能な薬剤は多いので、同一系統薬剤の連用とならないよう計画的な薬剤散布に努めてください。
キャベツ
- 黒腐病
風雨や強いかん水により跳ね上がった土壌中の病原細菌が、強風や虫害などで生じた葉の傷や葉のへりの水孔から植物に侵入します。その後、葉縁部に向けV字型に広がる黄色病斑を生じ、進展すると株全体が腐敗します。周囲への二次伝染は、病斑部の病原細菌が風雨で飛散して起こります。今年は9月上旬の降雨後に各産地で発生が見られ、今後に降雨があれば発生がやや多くなる可能性があります。
【対策】
細菌病のため発生後は急激に株全体に広がり周囲の株にも伝染しますので、ほ場の排水対策とともに薬剤による初期防除が重要です。降雨前後にクプロシールドやキノンドーフロアブル等の銅剤【M01】を下葉にかかるよう予防散布するとともに、発生があれば速やかにカスミンボルドー【M01+24】やバリダシン液剤5【U18】、カセット水和剤【24+31】など抗生物質を含む治療効果のある薬剤を散布し、感染拡大を防ぎましょう。
- ハイマダラノメイガ
各地で発生が見られます。今後の気温も平年より高い予想から、定植が遅い作型では例年以上に発生に注意してください。本虫は、作物の生育初期は中心葉の生長点部に潜って加害するため発見が遅れやすく、生育が停止したり正常に結球しない場合があります。生育中期以降は葉柄内への食入被害が多く、糞の排出や葉柄が垂れ下がります。
【対策】
定植後は早期発見に努め、ディアナSC【5】やプレバソンフロアブル【28】などを散布しましょう。なお、次項のヨトウ類との同時防除が可能な薬剤は多いので、同一系統薬剤の連用とならないよう計画的な薬剤散布に努めてください。
野菜、キク
- ハスモンヨトウ
本虫は広食性かつ食害量が多く、昨年や一昨年のように多発すると甚大な被害になります。今年は昨年ほどの発生量ではありませんが、県からはすでに注意報が発表されています。現在、被害が少ない地域でも高温のため例年より遅くまで飛来が続く可能性があり、しばらくは継続的な防除が必要です。
【対策】
老齢幼虫は薬剤の効果が低下するので、卵塊を除去しましょう。若齢幼虫集団で加害し、白変葉や葉脈を残した葉などの被害がみられます。早期発見した場合、薬剤を散布しましょう。防除薬剤は多く、キャベツではアニキ乳剤【6】やコテツフロアブル【13】、プレオフロアブル【UN】、グレーシア乳剤【30】、ブロフレアSC【30】などがありますが、各作物で適用農薬は違いますので薬剤のラベルの表示事項を必ず確認してください。また、本虫は薬剤抵抗性を獲得しやすいので、若齢幼虫への効果が低ければ他の系統に変更してください。なお、後述のオオタバコガやシロイチモジヨトウが同時に発生する場合もありますが、個別の害虫ごとに防除を実施するのではなく、同時防除を考慮して薬剤を選定し薬剤使用回数を必要最少限に抑えるとともに、系統ごとのローテーション防除により薬剤抵抗性の発現を防ぎ、効果の高い薬剤を温存しましょう。
- シロイチモジヨトウ
以前は主にネギの重要害虫でしたが、最近では多くの野菜類や花き類、豆類での被害が報告されています。今年も昨年程ではないものの誘殺数や発生量が多い地点があり、県ではハスモンヨトウと同様に注意報を発表しています。本虫はハスモンヨトウと同様に卵塊を産み、若齢幼虫は集団で加害しますが、幼虫はハスモンヨトウより一回り小さく、側面に白っぽい横線があります。ハスモンヨトウ幼虫の特長である頭部後方にある一対の黒紋はありません。
【対策】
ハスモンヨトウと同じく卵塊を除去したり、若齢幼虫が集団で加害しているときに防除しましょう。本虫に適用のある薬剤はネギ以外はまだ少なく、作物によって適用薬剤はかなり違いますので留意してください。ハスモンヨトウが同時に発生していれば、ハスモンヨトウの防除を主にして薬剤の効率的使用に努めてください。ただし、一部のジアミド系薬剤【28】などで感受性が低下した事例があり、ハスモンヨトウ対象に防除してもシロイチモジヨトウが残る可能性もあり、その場合は別系統の薬剤を使用してください。
- オオタバコガ
今年は発生時期が早く世代を重ねて多発する可能性があったため、県では7月に早期発見と防除を呼び掛ける注意報を発表しています。本虫はヨトウ類と違い単独で行動し花蕾や結球内に潜る性質があるため、発見が遅れやすく薬剤も効きにくくなります。
【対策】
幼虫は集団で加害することはありませんので、数頭でも発生を確認すればほ場全体で発生している可能性があります。早期発見による早期防除を徹底しましょう。特にキャベツ、レタスなど結球作物では内部に潜ると防除が困難になりますので、結球初期までに予防散布しましょう。キクでは着蕾後に加害されやすいので、着蕾以降は早期発見と予防散布に努めましょう。なお、被害部位に卵や幼虫が付着している可能性があるため、残渣は放置せずほ場外へ持ち出し処分してください。各作物の適用薬剤はハスモンヨトウに比べ少ないので、ラベルの表示事項を確認するとともに、同時に発生する場合があるヨトウ類との同時防除も検討して薬剤を選定してください。
施設トマト
- コナジラミ類、黄化葉巻病
近年、コナジラミ類が再び多発しています。今年も高温が続いたことから屋外での発生は多く、トマトを始めとする施設野菜への飛び込みは気温の低下とともに増加すると予想されます。多くの作物でコナジラミ類の多発により排せつ物によるすす病が発生しますが、トマトでは黄化葉巻病や黄化病の病原ウイルスを保毒した少数のコナジラミが多くの株にウイルスを感染させるため、他作物以上に防除の徹底が必要です。黄化葉巻病はタバココナジラミがウイルスを媒介しますが、本虫は多くの薬剤に対し抵抗性を獲得したバイオタイプQ(バイオタイプとは、外観は同じだが遺伝子型や生物学的特性が異なる系統)が優占しています。また、近年発生が多い黄化病は、タバココナジラミとオンシツコナジラミが媒介します。
施設イチゴ
- 炭疽病
本病は気温が低下すると発生は少なくなるのですが、今年は10月も高温傾向と予想され、本圃では例年より遅くまで発生が増加する可能性があります。葉の黒色病斑や萎凋症状だけでなく、茎や葉柄にわずかな黒色の楕円形病斑があればその株は感染しています。
【対策】
薬剤による発病後の治療は困難なため、葉かき時など管理作業時に株全体を観察し、発病株や発病が疑われる株は除去します。病原菌の分生胞子は、水滴の飛散とともに周囲に広がり伝染しますので、灌水チューブなどから水が葉面に跳ね上がらないよう注意します。また、薬剤散布時も過剰な散布水量にならないようにします。地床では排水の徹底、高設では不要な下位葉・古葉を摘除し湿度を下げましょう。摘葉作業は晴天時に行います。薬剤防除は耐性菌が発生するリスクが少ない保護殺菌剤を主体とし、ローテーションによる予防散布に努めます。保護殺菌剤にはベルクートフロアブル【M7】やオーソサイド水和剤80【M4】、ジマンダイセン水和剤【M3】などがあり、治療効果もある剤としてニマイバー水和剤【1+10】などがあります。
- ハダニ類
近年、ほ場間で発生量に差が大きい傾向があり、今年もすでに多発したほ場も見られます。この時期に多発したほ場は、育苗ほから本虫が持ち込まれ高温で増殖した可能性が高いと思われます。今後も気温は高い予想から、発生ほ場ではさらに本虫が増加し、冬季に一時的に減少しても翌春には再度多発する可能性があります。
【対策】
コロマイト水和剤【6】、ダニコングフロアブル【25B】、マイトコーネフロアブル【20D】など適用薬剤は多くありますので、同一系統の連用は避けるとともに使用回数は年1回程度にとどめ、薬剤抵抗性の発達を防ぎましょう。また、抵抗性が発現しにくく使用回数の制限がないピタイチやエコピタ液剤、サフオイル乳剤などの気門封鎖型薬剤を活用しましょう。チリカブリダニ(チリガブリなど)やミヤコカブリダニ(ミヤコバンカー等)など天敵農薬を利用する場合は、薬剤防除でハダニ類の密度をできるだけ低下させてから導入します。導入後は必要に応じて天敵に影響が少ない薬剤を使用しますが、影響日数に関しては販売店や指導機関等に確認してください。
☆薬剤名に続く【 】内の数字や記号はIRACコード(殺虫剤)、FRACコード(殺菌剤)で薬剤の系統を表し、同じ数字や記号は同じ系統の薬剤です。農薬は使用する前にラベル等で登録内容、注意事項等を確認してからご使用ください。
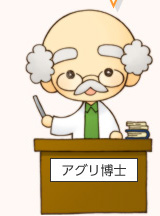
- 2025/10/23 今月の防除ポイント概要を更新しました。
- 2025/9/29 今月の防除ポイント概要を更新しました。"
- 2025/9/1 今月の防除ポイント概要を更新しました。
- 2025/7/31 今月の防除ポイント概要を更新しました。